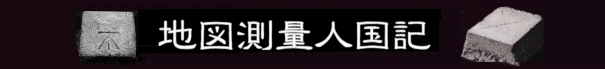|
藤島常興は、文政12年に下関市長府惣社町の藤島家に生まれた。
「長州藩士は、早くから自分の考えた判断のもとに行動する習性を持っている。・・・つねづね大きな仕事をしたいと願い自己顕示欲が極めて強い」のだとか(「県民性の日本地図(武光誠著)」)。
なるほど、首相を輩出する土地柄にうなずけるものがあるような気もするが、同じ長州の藤島常興にもそのような特質があったのだろか。
藤島家は、山口の大内義興に仕え、大内家滅亡後は毛利家に仕えて神社社殿の金具類調製などをする金工であった。
常興は、成人してのち江戸に出て、刀装小道具および鐔(つば)を主とする金工彫金のことでは、当時日本で最高と言われた後藤一乗(1791-1876)に金属彫刻を学んだ。さらに、一般には韮山反射炉築造のことで知られている伊豆・韮山代官江川英龍(坦庵1801-1855)に西洋兵学などを学んだという。
兵学の師となる江川英龍の父英毅は、当時の知識人・文化人との広い交流のあった人で、伊能忠敬や間宮林蔵とも交流があり、測地・地理にも明るかった。伊能忠敬測量隊の伊豆測量に際しては代官として、これを支える立場にあり、忠敬から専門書を借りるほどの関係にあった。その関連からか、英龍もまた測地・測量に明るかった。その英龍から兵学を学んだ常興は、兵学と深い関連がある測地・測量のことも学んだと考えられ、しだいに砲術や測量機器の研究を始めることになる。
明治5年工部省勧工寮に出仕、明治6年(1873)オーストリアのウイーンで開かれた万国博覧会に参加し、自ら製作した測量器を出品し有功賞を受けた。そのときの測量機器がどのようなものであったのだろうか。
このウイーン万国博覧会は、明治政府が始めて参加したもの。その派遣団には、諸外国の最先端技術を調査し、技術を学ぶことを目的とした技術伝習生も含まれていた。地図・測量のことでは、のちに内務省地理局勤務となり、多くの銅版や石版技術者を育成した、岩橋教章もその一人である。このとき常興は、派遣団の佐野常民副総裁から、引き続き同国において測量機器と船舶用磁石の製造技術の伝習することを命じられて滞在することになった。昼は同技術の、夜は幾何製図などの習得にも努めて、明治7年5月に帰国した。
同7年内務省地理寮に転任し、「測量機器伝習録」を著して、測量機器の製造を建言したという。同年工部省工作局へ転任し、測量器(セキスタント)・理学器の研究・製造にあたった。その後、数度の内国勧業博覧会に出品するとともに、審査官を兼務した。同10年(第1回)には尺度目盛器、同14年(第2回)には理化及び測量器を出品し賞を受けた。
同10年に工部省を辞した藤島は、翌同11年(1878)子常明とともに測量器・理学器の製造場を東京八官町に興した。同15年には、幾何図学の教科書を著し、同16年には、この製造場を藤島製器学校とし、自ら校長となって機械器具製造技術の指導に当たった。
故郷への思いがあったのだろうか、同24年には学校を次子常之に譲り下関長府に帰郷し、ここでも測量物理化学等の器械工場を開設し、特に測量器について舶来品をしのぐ精巧な製造に成功したという記録があるが、どのような機器であったのか詳細にたどり着いていない。
一方で常興は、少年時代に狩野芳崖の父晴皐(せいこう)に絵を学んでいたことから、同世代の芳崖とは幼馴染であった。日本画の大家となる芳崖は、明治10年に常興を頼って上京している。また同じ日本画の下村観山も明治14年に上京し、しかも常興に画を学んだという。絵画のことでも優れたものを持っていたのだろう。明治6年のウイーン行きのことを記した近藤真琴の「墺行日記」の中には、常興がアドリヤ海でスケッチをし、真琴に賛を求めたとの記述がある。このときは、船旅の暇に任せて絵のことをしたのだろうか。
それ以前、文久3年(1863)に長州藩がアメリカ商船に発砲したことをきっかけで始まる馬関戦争の際には、外国連合艦隊が下関砲撃をする様子「馬関戦争絵図」を描いていて、同図は金工品などとともに長府博物館に所蔵されている。
常興は、封建期の伝統職人技術を土台にヨーロッパ留学で習得した西洋技術により、測量機器・精密機器製造に功績を残した。明治31年70歳で亡くなり、墓は下関市の功山寺墓地にあり『心遠斉之墓』とある。もと計量研究所が所蔵していた藤島常興製作の尺原器は、国立科学博物館に寄託されている。
【参考文献】
「墺国博覧会賛同紀要」田中芳男、平山成信編
もどる
|