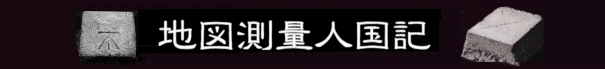|
箕作省吾は、文政 4年に水沢領主伊達将監の家臣佐々木左衛治秀規の次男として生まれ、幼名を高之助、のちに省吾とあらためた。
省吾の生まれた水沢は、仙台支藩の城下町で、水沢伊達氏が学問に力を入れ、藩校の充実や家塾を奨励していたことから、箕作省吾のほか、高野長英、後藤新平、斉藤実などの人物を輩出したといわれる。
省吾は、11歳のころから蘭医坂野長安について漢学と医学を学んでいた。ところが、14歳のときに父母が相次いで亡くなった。
16歳のとき江戸へ遊学、そして京都へ上り儒学を学んだ。その際、各地の地勢、交通、風俗、名勝・古蹟などに触れ、その後の地理学への素地が作られたという。再び郷里へ帰り、坂野長安の下で蘭学を学ぶうちに、箕作阮甫(げんぽ)の偉大さに触れ、彼に師事するため再び江戸に向かった。
箕作阮甫(1799- 1863)は、美作国津山の藩医の次男として生まれ、京都で漢方医学を学び、藩医を継いで江戸詰めとなったのちは、西洋医学を学び、シーボルトの江戸参府に際しては、彼と接見した。省吾が師事する以前、天保10年(1839)には幕府天文台に出仕し、蕃書和解方として、医学書のほか地理書の翻訳、著作にあたっていた。
箕作阮甫への師事が適って蘭学を学んでいた省吾は、その才を見込まれて三女の婿養子となった(弘化2年1845)。次第に地理学、特に世界地理に興味を持つようになり、「新製輿地全図」「坤輿図識」などの編纂を通して、世界各国の位置、国勢、風俗習慣、宗教、産業などを紹介した。
「新製輿地全図」は、フランス製の世界地図からの最新の情報を盛り込んだ銅版の両半球図である。「坤輿図識」は、五巻三冊からなる地理書である。
その後、「坤輿図識補」 4巻の翻訳・編纂にあたり結核を発病し、喀血により原稿を血に染めるほどの病を押しての作業に病身は耐えられず、弘化3年25歳の若さで亡くなった。
世界地誌「坤輿図識」と世界地図「新製輿地全図」は、鍋島斉正や井伊直弼らが外交の指針とし、吉田松陰や桂太郎がこれによって大志を立てるなど幕末期の志士らが競って読み、親しんだといわれる。
ちなみに、箕作阮甫には三人の娘がいて、それぞれ子弟などに嫁いだ。その縁戚は、地理学者箕作省吾、洋学者箕作秋坪(しゅうへい)を初めとして、教育者、動物学者、歴史学者などが輩出する学者家系であることが知られている。
もどる
|