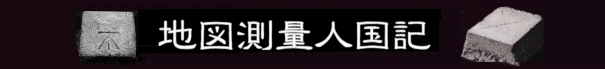|
茨城県には、長久保赤水、間宮林蔵、長島尉信、沼尻墨遷、鷹見泉石というように測量・地図に係わるものが多く出ている。その理由はどのようなことだろうか。
水戸藩士の気質あらわすことに「水戸の三ぽい」という言い回しがある。それは、理屈っぽい、骨っぽい、怒りっぽいというものである。それはそれ、測量・地図に限らず多くの知識人を輩出させる基盤となったのは、何と言っても徳川光圀の「大日本史」編纂に見られるような教育重視の気風ではないだろうか。
江戸時代後期の人であった小野友五郎は、幕末期の傑出したテクノクラート(技術的あるいは専門的政策立案能力をもつ行政官僚)であって、測量家だけの人ではない。
彼を表現するものとしては、和算家、数学家、天文家、造船設計家、航海士、財務・会計家、製塩技術家、そして水路・鉄道測量家といったものがある。しかし、数学と測量を基礎とした政策官僚であったことも、疑いない事実である。
小野は、文化14年)に、常陸笠間藩士の家に生まれた。生家は小守氏、養家は小野氏であったが、いずれも貧しい下級藩士であったことから、幼いころは教育機会には恵まれなかったが、自らが下級藩士となる16歳のときから、夜学として、甲斐駒蔵に和算を学んだ。
後に小野は、幕府の技術官僚として活躍し、勘定奉行並にまで昇進し、ごく下級藩士の出自のものとしては異例の将軍との単独謁見の栄も受ける。文字にすれば、「謁見の栄を受けた」と簡単なことになるが、厳格な身分社会のこのときに、将軍に拝謁するということは、途方もないこと。直上の藩主でさえも、かなわぬことであった。
驚くべき昇進のことを含め、多くの実績を残す根底には、卓抜した数学の力と科学的な判断力、そしてこれらの才を見抜き、しがらみの無い異例の抜擢を行う監督者と、それを可能とした当時の時代背景といったものがある。
彼は郷里での一時期、地方(じかた)手代になっている(1837 20歳)。地方は、町方に対してのことで、農政に必要な土木や測量を行う者のことである。もちろん、その測量の最終成果となる藩内村落の地図作製も行なう。地方に就いているということは、甲斐から学んだ和算の実力が認められたということである。その後の江戸行きのことも(1841)、この延長にあって、地方としての業績が認められ、上司に推されてのことである。
江戸詰めとなった小野は、甲斐の師である長谷川弘(ひろむ)から和算を、伊豆韮山の江川英龍から、造砲術や洋式砲台の設計法などを学んだ。それは、笠間藩下屋敷での本来のお勤め合間のことである。
嘉永五年(1852)には、師の甲斐駒蔵とともに地方測量術の書「量地図説」を著した。同年、江戸で天文方出役に就いた。これには、師である江川英龍から和算の才を見込まれて、その推薦があったから。当初は天文方足立信行の定員外雇いといった立場にあった小野であるが、編暦の職務を行いながら、当時は天文方の範疇であった洋書の翻訳にも従事した。そして、足立信行らとともに、蘭人スワルトの航海術書を「渡海新編」として翻訳した(1854)。
さらに、海軍士官養成を目的とした海軍伝習所が長崎に開設されると、小野はそこでの航海術専修を命じられる(安政2年 1855)。このとき、異例の修学の機会を与えたのは、「渡海新編」である。
海軍伝習所では、オランダ人教官から六分儀による測角、クロノメータの較正といった実用的な天文航海術を学んだ。安政七年(1860)、日米修好条約の批准書の交換のために遣米使節が派遣されることになった。咸臨丸での渡米時の編成表には、「測量方兼運用方 小野友五郎」とあって、現在の航海士に当たる業務を担当した。そのとき、同行した米人ジョン・M・ブルック海尉は、小野ら一部日本人測量方が、天文測量や航海術に熟達していることに大いに驚いたという。
その咸臨丸の遣米使節は、日米修好通商条約の批准書交換のほかに小笠原群島の調査という使命を併せ持っていた。しかし、太平洋初航海という難敵に、往復路ともその命を果たすことは出来なかった。
当時小笠原群島は、捕鯨船の補給基地として外国人が居住しており、英米は領有あるいは植民地化をもくろんでいた。従って、小笠原の奪回、すなわち群島の測量と地図作製を行い、古記録との参照などにより古来の領土であることを主張することが求められていた。
帰米した小野は、咸臨丸艦長として小笠原群島の調査・測量を開始する。
これに参加した測量方には、海軍伝習所の塚本桓輔(塚本明毅)、咸臨丸渡米に同行した松岡盤吉などの技術者の名が見える。この調査では、天測、海岸線測量、深浅測量などを実施した。伊能忠敬以来の日本領土の実測図となる小笠原群島図を完成させた(1862)。この成果などによって、諸外国を納得させ、小笠原の日本領有は確たるものとなった。
明治維新後は、民部省鉄道局に出仕し(明治3年)、路線測量あるいは路線選定の現場に永くいた。この間並行して塩業振興にもあたった。他にも、天文台の開設、天文暦の編纂、皆既日食観測の国際協力などについて建言するなど、小野友五郎は、最晩年まで先取の視点を持ち続けていた人である。
【参考文献】
「小野友五郎の生涯」藤井哲博著 中公新書
もどる
|