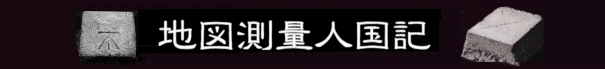|
市川方静は、天保5年に現福島県白河市に生まれた。市川の家は代々白河藩主に仕える家柄であったという。
白河の地は、和算が盛んな地であって、市川も坂本数衛門などから最上流和算を学んだ(万延2年のころ 1861)。ところが、彼の興味は和算や測量にとどまらず、天文、易学、鍼治、和歌、茶道、謡曲、講談にまで及んだ。中でも測量のことには早くから関心を示し、「国力を開発する計画はさまざまあるが、急を要するのは道路の整備による運輸の推進である。このためには測量術が必要である」と、その重要性を常々述べていたという。
市川が測量術を、どこで、誰から習得したかは明らかではない。しかし、和算の初歩では長さを測る、面積を求めるといった日常的な計算をするための算術が主となるが、さらに進むと幾何図形、対数や級数にも及び、この和算を社会生活の中で実践できるのが測量であるから、そのような中でごく自然に測量のことを知ることになったのだと考えられる。
安政5年(1858)24歳のとき、はじめて測量器(現在のトランシット)を製作し、「調方儀」と名づけた。その後、改良され「市川儀」などと改名され、明治20年には「方静儀」という名で売り出された。
明治13年9月21日朝野新聞には、「市川方静が調方儀を発明」の記事がある。そこには、「・・・往々寝食を忘るるに至りしより、世間には測量狂人なりと嘲るを更に意とせず、ついに調方儀という器械を発明・・・」ともあるように、測量機器開発に熱意を持って臨んでいた。同紙には、「機器の製造を東京の機器製造師大隅源助に依頼し、旧白河藩士で測量家の伴勘三郎とともに実地試験をした」ともある。
伴勘三郎のことは不明だが、大隅源助は東京浅草にあって、伊能忠敬も使用した江戸の時計師大野規貞、規行父子の製作した測量機器の残された商品カタログともいえる「引き札」から見る限りのことだが、この当時は一般技術者向けに測量器具を製作し販売していたと思われる。
市川は、これ以前明治12年のころには、福島県属として土木工事に従事していたから、使用する測量機器に対して何らかの不満を持ち自ら開発しようと発意したと思われる。また、使用測量機器の購入その他のことで、大隅との交流が芽生えたとしても不思議ではないだろう。
明治14年にはこの職を辞し、以降は白河で数学や測量学の教育にあたり、3500人にも及ぶ門下生を世に送り出したという。
明治20年(1887) 8月19日、この時新潟県から茨城県にかけて皆既日食が予想された。のちに初代の中央気象台長になる内務省地理局の荒井郁之助、東京気象学会を設立し会長となる正戸豹之助、そしてのちに陸地測量部に転じる杉山正治らの一隊が、新潟県三条市の永明寺山で観測にあたった。この観測で、接触時刻観測とコロナ写真の撮影に成功し、これをもって日本も本格的な近代的日食観測ができるようになったのである。
同日の観測は、栃木県黒磯市には初代の東京天文台長の寺尾寿、千葉県銚子市には内務省地理局の小林一知、そして福島県白河市の小峰城址にはアメリカから来日したドット教授を含む数人の天文学者が観測準備をしていた。市川も小峰城址での観測に特別参加が許された。三条市永明寺山以外での観測は悪天候のため、ことごとく失敗に終わった。白河市小峰城址のドット教授の観測隊も悪天候のため観測できなかったのだが、飛び入り参加した市川だけが雲間から皆既日食を捉えスケッチにも成功したのだという。もちろん、その時使用した望遠鏡は、自身が開発したものだったのだろう。
市川の学問その他への興味には幅広いものがあったことは先に述べたとおりである。中でも、易学のことには大きな関心を持っていた。過去には、天文総本家土御門家が陰陽道のことをしていたことでも分かるように、天文と易学のことは強い結びつきを持っていた。市川もまた、天文・和算の延長で易学もしていた。あの皆既日食観測の日の天候を、気象学ではなく易学によって悪天候であると占ったというエピソードが残っている。
後半生の大部分は不明だが、明治36年に病死し、福島県白河市金屋町 妙徳寺に葬られた。子息もまた、土木技師として鉄道・橋梁の建設に従事し、測量とともにあったという。
【参考文献】
「測量術の進歩に寄与した市川方静」「日本の想像力」NHK出版
もどる
|