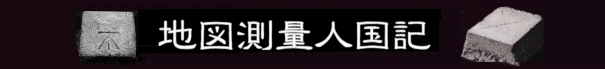|
都築弥厚は、明和2年に現在の安城市和泉町本竜寺付近で、米の売買、酒造業、新田経営などを営む豪農の家に生まれた。父也更(1741-1817)は、一代で巨万の富を築いた人で、最大時の酒造量は全国屈指のものだったという。
二代目であった弥厚は、豪農の主らしく、これを経営する傍ら芭蕉の流れを汲む師について俳句を学び、絵や漢詩にも興味を持った。残っている俳句は30数句、そして蘭や梅の絵も描いた。
弥厚は、享和3年(1803)全国測量に際してこの地を訪れた伊能忠敬を案内している。その様子は、「測量日記(4月18,19日)」に「鈴木弥四郎と云う者…」と記されている。伊能忠敬の測量に際しての地方の測量技術者などの訪問は、越中の石黒信由や讃岐の久米栄左衛門などがあり、大いに意見を交換し、親交を深めている。そして阿波の岡崎三蔵に至っては、長男を偽名で測量隊に参加させ、技術を盗み見しようとしたことなどが知られている。弥厚もまた忠敬の大事業の遂行について、あるいは測量技術について意見の交換をしたのであろう。
その弥厚が、和泉村の北東に広がる五ケ野、安城野と呼ばれる地の開発のため、矢作川の水をその台地を開削して貫流させる用水路計画を企てたのは、40代半ばの頃だといわれている。そして、57歳になった文政5年(1822)石川喜平の協力を得て用水路の測量に着手した。忠敬測量のとき見聞きしたことは、同僚の喜平にも伝えられたであろう。いや、弥厚に同行して測量技術について知識を深めていたかもしれない。
測量が終わったのは、4年後の文政9年であった。測量の完成までこれだけの長期間を要したのは、用水によって水害を招くのではないかなどといった、地主・農民の誤解からきた抵抗があったからである。そして、翌年には幕府勘定奉行に「新開願書」を提出するのだが、許可が下りるのは、さらに7年後の天保4年(1833)のことであった。
その年弥厚は68歳で病没する。用水路はおろか、一坪の開墾も実施しないままの他界であった。一枚の測量図を残して、事業は挫折した。
それでもなお、安城市和泉町の八剣神社の南、半場川に沿った小さな林の中(和泉町弥厚公園)には、上下姿に両刀を携え右手に扇子を持った代官姿の都築弥厚の銅像がある。
都築弥厚は明治用水最初の計画者であるから。
用水路の測量を担当した石川喜平は、碧海郡(現安城市)の和算家であった。喜平は、同じ碧海郡の関流の清水林直に和算を学び、免許を受け、村の内外には多くの門弟を持っていたというほか、詳細は不明である。
残された書籍の多くは和算と天体観測記録など暦に関するものが多いが、僅かに測量に関するものも含まれている。その中には、喜平の手による水路計画図(明治用水土地改良区所蔵)があり、流路と台地の輪郭そして水路計画線とともに、主要な村々の間は線で結ばれ、朱で距離が書き込まれている。使用した測量器具(木製の見盤)は、明治川用水会館に保管されている。見盤の上部には十二支(方角)が刻まれ磁石も埋め込まれていたようである。また、取り付けられた小さな二本の角材には中心に小穴があけられており、これにより目標方向を視準し、磁石により方位を読みとったと思われ、金属製の測量機器が出現する以前に地方測量で使用された木製見盤の典型である。
弥厚の用水計画は、地主らの抵抗もあって成功しなかったが、それから約50年を経て、岡本兵松、伊予田与八郎らの新しい提案者の出現により再度出願され、明治12年(1879)に着手、翌年には通水を開始した。岡本らは、弥厚の計画を継承し、計画に疑念を持つ村々の説得に力を入れたという。用水と以後の整備によって新しく開かれた田は、約6,000haにもなり、「日本のデンマーク」と呼ばれる安城の農業はここから始まり、弥厚の永年の夢が実現した。
明治川神社には、都築弥厚、岡本兵松、伊予田与八郎らが祭神として祀られ、石川喜平の水路計画図や測量器具などが保存されている。
【参考文献】
「江戸時代の測量術」岡崎市博物館
もどる
|